中西輝政著、「国民の文明史」を読んでいます。
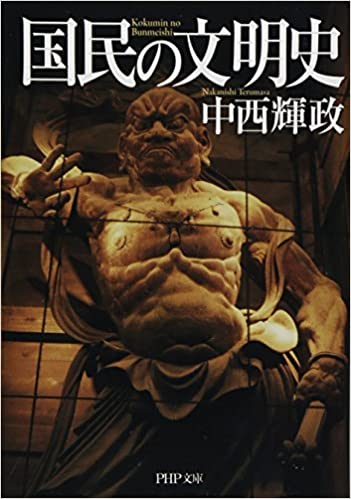
日本の歴史をたどりつつ、欧化の流れに日本人はどう対峙したのか、記されています。
その一つ、日本の哲学のこと。
「善の研究」
日本が欧米列強に肩を並べようと近代化に邁進していた明治時代。しかし「哲学」という言葉が翻訳されたばかりの日本では、およそ自分たち独自の哲学を構築できるなど思いもよらないことでした。そんな時代に、禅などの東洋思想や西洋の最新思潮と格闘しながら、日本だけのオリジナルの哲学を独力で築き上げようとした人がいました。それが西田幾多郎(1870-1945)です。彼の代表作が「善の研究」。
「生きるとは何か」「善とは何か」「他者とどうかかわるべきか」といった、人生の根本的な問題を深く考えたものです。
日本に押し寄せる欧化の波の中で、ドイツ哲学を必死に日本化(和魂洋才化、換骨奪胎)したのが西田幾多郎ということです。
それについて、中西はこんな言い方をしています。
・・・西田幾多郎一門が、西田幾多郎のいちばんの核心部分を、継承しえなかったというと、では誰が継承したのかということになる。私は、それは京都大学でも理学部や工学部の人々だったと思う。ノーベル賞を受賞した湯川秀樹、福井謙一を思い出してもらえばよい。彼らは、西欧の自然科学の体系を深く無自覚な「直観力」によってわがものにして、それに日本独特の「武的感覚」や「匠の精神」を発揮して、ギリギリまで追い詰めて、換骨奪胎してゆく。・・・・(中略)
湯川秀樹や福井謙一の着想とか、直感というのは、実に日本的なものである。彼らが使う「直感」というのは、「えもいえぬ」説明できないものであり、実際、その底には西田の言う「絶対無」があったと、湯川や福井は自らの著作で語っている。それはたしかに「日本の科学」だったのである。・・・
日本で成功する科学、それも根源的な日本がベースとなっている、そんなことも言っているわけです。
おそらく、今の日本でも、なにを研究したらいいのか、どんな商品を開発したらいいのか、悩み苦しんでいると思います。でも、日本的な直感、それを信じてやり続けるべきということになると思います。
日本人が持っている直感、これはいいね、こうあるべきだよね、という、すとんと心に落ちて、理解ができるもの。それをやればいい。
海外でもいろいろ研究開発は進んでいますが、情報は情報として収集し、理解し、でも換骨奪胎して、日本人である自分の感性に合うように変えてやって、単純にこれはいいね、という研究、商品開発をやってゆけばいい、
そう思います。
「国民の文明史」を読む(9)(終わり) 完