中西輝政著 「国民の文明史」を読んでいます。
前回は、日本文明における「換骨奪胎の超システム」について記しました。
換骨奪胎、難しい漢字の羅列なのですが、
換骨奪胎(かんこつだったい); 骨を取り換え、子が宿る胎を奪(うば)いとるという意味から、先人の発想や形式を利用しながら、自分独自の作品につくり直すこと。明治の福沢諭吉も使った言葉ですが、外から流入する文化、技術、文明は無条件で受け入れるのではなく、日本にあうように変えて、あるいは部分的に拒絶してから、受け入れる、ということです。
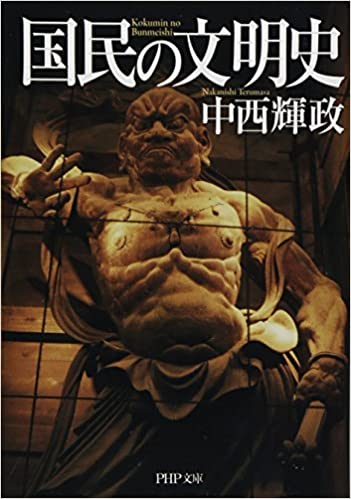
中西はこのシステムの動作を日本歴史の中で検証しています。
ここでは、自分がもっとも関心が高い江戸、明治、大正、昭和の話を書いてみることにしてみます。
もともと司馬遼太郎の歴史小説を読んで、その司馬史観に触れ、これが日本人というものか、と理解しようとしたところ、昭和の時代で、空白になってしまった。それを埋めたくて中西の「国民の文明史」を読んでいるのです。
まず、江戸時代についてです。
弥生的な戦国時代が終わり、弥生的な徳川家康が、江戸幕府を開きます。これは、源頼朝による鎌倉幕府をまねたものです。そのあと、17世紀の日本では、自生的に「江戸文明」が興隆することになります。この間に、中国から伝わった儒教を、換骨奪胎することで日本独自の儒学が学ばれるようになります。この儒学は国学へ変化してゆき、幕末の維新思想につながってゆくことになります。これは、「武士道」の形成とも重なり、日本人のアイデンティティーとなってゆきました。
そして、江戸時代という縄文化から、明治維新という弥生化に向かうことになるわけです。
この中西の議論は、ほぼ、歴史小説家の司馬遼太郎が考えていた歴史観と同じように思えます。江戸時代の教養が儒学教育中心で、その教育がベースとなって明治維新が為された、ということ。司馬の小説を読んで感じる、わくわくとした躍動感、あるいは読後のすがすがしさの一部は、おそらく、この儒学教育、武士道の空気から漂ってくるものだと思います。
次は明治の場合。
国民の文明史を読む(4)(終わり)